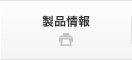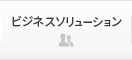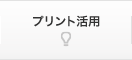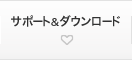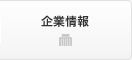課題を見つけ、解決する、"生きる力"を育むプログラマッピング


導入事例を動画でご紹介
プログラマッピング導入事例 横浜市立六つ川台小学校
導入背景
"生きる力"を育む、総合学習での先進的な取り組み

児童たちが将来、社会に出て問題が発生した時にどのように対処し、解決策を見出していくのか。他者と協力しながら自分の考えを適切に表現しつつ、共有する力が重要になる。
実社会でいずれ必要となるこうした"生きる力"を育もうと、小学校では先進的な取り組みが行われている。横浜市立六つ川台小学校・6年生の総合学習の時間で、プログラマッピングを活用した授業も好事例の一つだ。技術的なスキルだけでなく、創造的思考やチームワークを身につけることをめざした先進的な取り組みについて早速、見ていこう。
選定理由
手軽な使い心地、子どもの可能性をより伸ばせる

横浜市立六つ川台小学校 教諭 有馬広貴氏
6年1組の担任を務める有馬広貴教諭がプログラマッピングを知ったのは、2024年3月~4月初旬ごろ。当時、総合学習の授業でプログラミングの活用を検討しており、教材を探していたところ、エプソンのプログラマッピングを活用した事例記事を発見。すぐに問い合わせをすることにしたという。
「タブレット端末にアプリケーションを一人ずつインストールできるところに魅力を感じました。自分たちのテーマを表現していくことが可能であり、児童一人ひとりが課題解決に取り組むことができると思ったからです」(有馬教諭)。
プログラマッピングの魅力
プログラマッピングは課題意識が生まれやすい

プログラマッピングという表現方法は、作品制作を通じて、自然と課題意識が生まれやすいと感じています。例えば、今日の発表では6年生のグループが立体物に投影し、映像に合わせてふすまが開き、そこから何かが出てくるという構成を作っていました。一方で、平面に投影するグループもありました。こうした違いを通じて、自分たちの映像作品の課題を見つけ、それを解決していく学びの流れが生まれます。また、他のグループの作品を見たり、各地で行われているプロジェクションマッピングと比較したりすることで、新たな気づきも得られます。さらに、今日のように校長先生やエプソンさんのようなプロの方から講評をいただくことで、より深い課題意識が芽生えるのも大きな魅力です。単に映像を投影することが目的ではなく、映像を通じて自分たちの作品や表現についてフィードバックを受け、それを糧に成長できることに魅力を感じています。
児童からの感想
教室から飛び出し、友達と協力しながら目的達成をめざす

6年1組の児童
児童の一人に、プログラマッピングの印象を聞くと、プログラミングとは違い、プログラマッピングは投影するところまでがセットになっている。また、第三者に見てもらうという前提で作っているため、動画に文字や声を入れる工夫を重ねたことが今までとは違ったと話す。
「実際に授業で取り組んでみると、最初は難しそうだと感じましたが、特徴を生かして工夫したいという好奇心が湧いてきました。それに前よりも工夫するために友達と相談する機会が増えました」
友達との話し合いを通じて、自分と同じ考えなら自信が持てるし、もし違う場合はどちらがより伝わるかを確認する良い機会になったという。また、コミュニケーションをしながら考えをまとめる力が身についたと振り返っていた。
今後の展望
自分たちで課題を見つけ取り組むところで自主性や協調性も育まれる
2月上旬に行われた6年1組の総合の授業では、1年生から6年生までの成長を伝えるプログラマッピングで作成された動画が教室や図工室、体育館などで投影された。有馬教諭は中間発表を通じて多くの意見を受け取り、次の課題を見つけてほしいと語った。
今後は最終発表会で、保護者や先生などを招待する予定。
自分たちの成長を伝えるべく、プログラマッピングの内容がさらに磨かれていくはずだ。今後さらなる児童たちの"生きる力"が伸び、次のステージに移行していくに違いない。

6年1組の発表を聞いて拍手する1組の児童たち

体育館でプログラマッピングに見入る児童たち

お客様のご紹介
神奈川県横浜市立
六つ川台小学校様

| 所在地 | 〒232-0066 神奈川県横浜市南区六ッ川3丁目65-9 |
|---|
導入事例PDFダウンロード
導入事例は、PDFでもご覧いただけます。
(約1.05MB)
製品に関するお問い合わせ・資料請求
エプソン販売株式会社
プロジェクターインフォメーションセンター
受付時間:月曜日~金曜日
9:00~17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
上記 電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、
042-503-1969までおかけ直しください。
商標について
本媒体上の他者商標の帰属先は、 商標についてをご確認ください。