- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
エプサイト
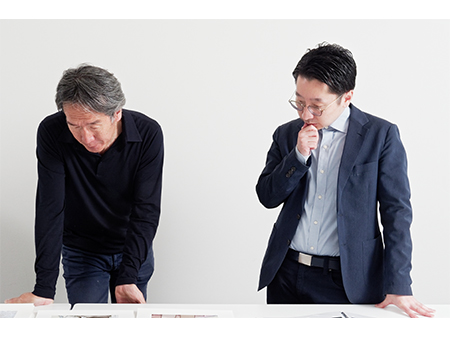
選考会の様子
2022年11月~2023年3月までの期間にエプサイトギャラリーにて写真展を開催する作品を選出する公募展選考会を行い、3組の出展者を決定しました。選出された作品と選考委員のコメントは以下のとおりです。
また、今後応募を希望される方へ選考委員からのアドバイスを掲載していますので、こちらもご覧ください。

日常の中のきらめいた瞬間を生捕りにしておくことは私を安心させる。
今そこにあるけど確実に消えてしまう情景を記録したい。
撮った写真を見るたびにその人や付随するものを思い出す。
私にとって撮ることは祈ることと似ている。
【プロフィール】
大森 めぐみ|Megumi Omori
2020年 多摩美術大学 美術研究科デザイン専攻博士前期課程を修了
2018年 「Shining in your eyes '18」Gallery916
2020年 「Shining in your eyes 2020」LE DECO
2020年 「Touch of Summer -夏の手触り-」ロロピアーナ銀座
2021年3月より雑誌「宣伝会議」のカバー撮影を担当
https://www.instagram.com/meg_omori/![]()

茅ヶ崎のビーチは、光と海と風と砂が終わることのない変化を見せてくれます。私は、その変化を追いかけ夢中になって写真にとどめましたが、もう一人の作者は自然そのものです。
自然に対する驚きと感謝の気持ちも含め、作品にまとめたいと思いました。
【プロフィール】
戚 羽豪(セキ ウゴウ)|YUHAO QI
2019年 多摩美術大学グラフィックデザイン学科 卒業
2021年 多摩美術大学大学院グラフィックデザイン専攻(写真研究室) 卒業
2020年8月 株式会社スパーキング アート スタジオを設立
https://www.sparkingartstudio.com/![]()
https://www.instagram.com/ugou_yhq/![]()

宗教の信仰を持ってないが、ずっと造物主の存在を信じている。
風景を眺めるとき、私たちの命や雑草のようなちっぽけな命、そして人間に創造された命のないものと一体どんな違いがあるのかを、よく考えている。
人間が創造している一方で、別の何かに創造されるものでもある。
「私たちが創るもの、私たちを創るもの」というテーマに沿って、造物主の存在、また生命に対して自分の思考を写真で証明したいと思う。
【プロフィール】
段 佳祥(ダン カショウ)|Duan Jiaxiang
1995年 中国 青島生まれ
2018年 山東芸術学院メディア学科ドキュメンタリー専攻卒業
2019年 来日
多摩美術大学大学院写真研究室在学中
https://www.instagram.com/viscaria16/![]()